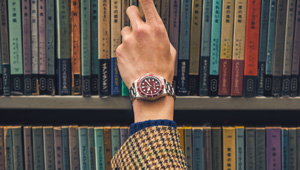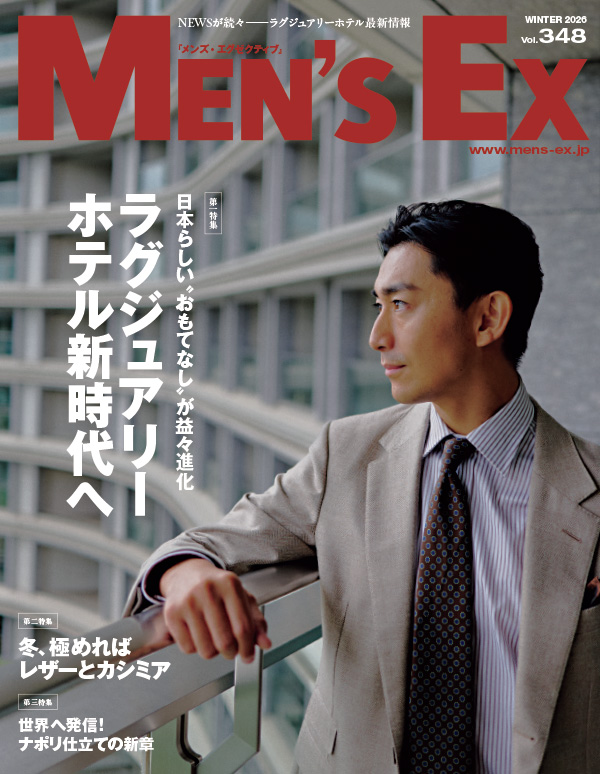【加藤綾子 一流思考のヒント】
第30回 ユニバーサル ミュージック 社長兼最高経営責任者 藤倉 尚さん[後編]

Profile
加藤綾子 Ayako Kato
1985年埼玉生まれ。2008年フジテレビ入社、看板アナウンサーとして活躍。’16年、フリーアナウンサーとなり女優としても活動。現在は報道番組『Live News it!』(CX)のメインキャスターを務めるほか、『ホンマでっか!? TV』(CX)にレギュラー出演中。
著書に『会話は、とぎれていい―愛される48のヒント』(文響社刊)など。
藤倉 尚 Naoshi Fujikura
1967年東京生まれ。メルシャンを経て、’92年ポリドール(現ユニバーサル ミュージック)入社。2007年に邦楽レーベル「ユニバーサル シグマ」のマネージング・ディレクターに就任。’08年に執行役員、’11年に常務兼執行役員、’12年に副社長として邦楽を総括。’14年1月より現職。一般社団法人日本レコード協会副会長も務める。

「BTSは英語で歌わないと世界で1位になれないルールをひっくり返しましたね」
(加藤さん)
加藤 ところでユニバーサル ミュージックは日本の外資系レコード会社では最大手で、本社はアメリカですが、日本とのビジネスの違いはどのようなところに感じられていますか?
藤倉 アメリカの人たちはいつもグローバルに物事を見ています。自分たちが見つけてきた才能を世界中で売ろうと思っている。だから、見ている景色もプランも全く違いますね。それとアメリカではパワーがあるアーティストが真ん中にいて、本人がエージェントを雇って、レコード会社も選びます。一方で日本の場合、アーティストは事務所とレコード会社と三位一体で一緒になって売っていこうというチームプレイが前提です。
加藤 グローバルで成功したという点では、まさにユニバーサル ミュージックのアーティストであるBTSが、韓国語の曲にもかかわらずアメリカのビルボードチャートでナンバーワンを獲得できた理由は、どこにあったんでしょう?
藤倉 第一に彼らが純粋にすごかったということです。先程のデータの話じゃないですが、どんなに素晴らしい戦略を立ててもアーティストと作品がだめだったら、売れませんよね。そういう意味でBTSはパフォーマンスも歌うことも喋ることも、言うまでもなくダンスもすごかった。他にも完璧な英語でコミュニケーションできるメンバーがいたり、様々な成功要素があったと思います。第二に韓国だけでなく、世界76億人に自分たちの音楽や映像を届けるために、TwitterやFacebookやInstagramといったSNSを研究して、いち早く取り入れていったのも大きかったと思います。韓国の映像制作のレベルと彼らのミュージックビデオのクオリティは本当に高くて、アメリカのアーティストやクリエイターが見てもすごいものがある。しかもグローバルで多くの人に見られるようになるとクリエイティブに力をいれることができるので、相乗効果も生まれます。
加藤 日本の中で日本の人に向けて作るものはやっぱり限られたものにはなりますよね。
藤倉 BTSは韓国語がわからない人にもダンスと映像で自己表現をしてメッセージを伝える圧倒的な力があったと思いますね。
加藤 とにかく英語で歌わないとグローバルで1位になれないというルールをBTSがひっくり返したわけですが、日本のアーティストが世界でナンバーワンを取るには何が必要ですか?
藤倉 例えば加藤綾子さんを世界で売る場合、今までは海外のユニバーサル ミュージックに頼んで、現地のレーベルと契約して、現地の仲間がラジオ局やテレビ局に宣伝してくれて、小さなライブハウスから始めて……というやり方しかなくて、要はものすごく時間も人も必要だったんですが、そうこうしているうちに人々が求めているものが変わってしまう。だからこそ、フォロワーを増やせば存在と作品を短期間に一気に伝えられるSNSというツールの台頭は大きい。日本のアーティストもそこで世界で戦うルールを身につける必要がある。逆にどんなに才能があっても世の中に伝える新しい方法がないと難しい時代なのかなと。
加藤 私もインスタグラムをやっていますが、世界を目指すということでなくても、伝え方をもっと研究しないといけないですね。
藤倉 わが社所属のアーティストでもPerfumeや久石 譲、イギリスに移住した布袋寅泰やアメリカを拠点としているMIYAVIも、みんな本気で世界を目指していますが、新しいルールで勝負をしていこうと話しています。
加藤 藤倉さんの経営者としてのあり方も伺いたいのですが、どう目標を設定して、それを達成するためにどのようなことを大事にされていますか?
藤倉 6年前に社長になったとき、当時のユニバーサル ミュージックはいわゆる外資系企業の日本支社のようなもので社訓もなかったので、自分たちが迷ったときに立ち返ることができる「人を愛し、音楽を愛し、感動を届ける」という言葉を作りました。それともうひとつ「Be ahead」という言葉を掲げました。どうしても日々、目の前のことで精一杯になりがちですが、自分も含めトップに属する人間は、仕事の9割は未来のことを考えたいなと。これはさっきお話しした妄想力にも繋がると思っています。