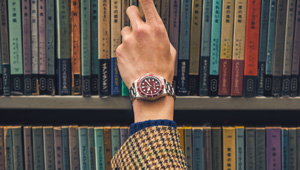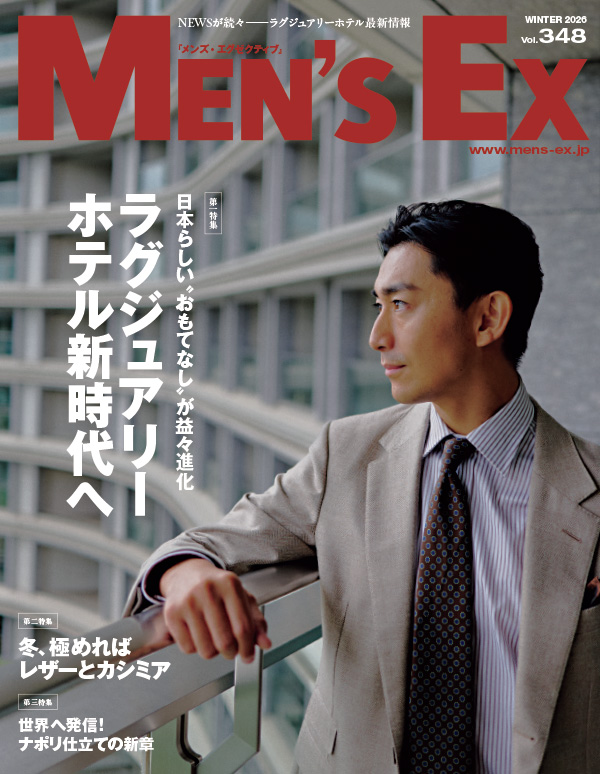コンセンサス化しつつある“電動車”による排出ガス削減
「地球温暖化対策」という名の下に、自動車業界が大きな変革を迎えようとしている。地球温暖化最大の要因は化石燃料を燃やすことで生じるCO2排出量である、と言われて久しい昨今。ガソリンやディーゼルといった化石燃料を燃やす内燃式エンジンを廃止して、自動車は“電動車”にすることで排出ガスを削減しよう、という流れがコンセンサス化しつつある。
そもそも電動車とは4つのカテゴリーに現在のところは分類できる。まず、内燃式エンジンと電池と電気モーターを組み合わせた、ハイブリッド車(HV)。そして、ハイブリッド車に外部充電を可能にさせた、プラグインハイブリッド車(PHV)。いずれも既存のガソリンスタンドで給油できるので、航続距離の不安が少ない。
車両からのCO2排出量ゼロを実現させるのは、車載タンクに充填した水素を大気中の酸素と反応させて発電し、電気モーターを駆動させる「燃料電池車(FCV)」。そして、多くの自動車メーカーがあいついで投入しているのがバッテリーで電気モーターを駆動する「電気自動車(BEV)」の4つだ。
ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車は内燃式エンジンを有しているため、先行きは暗いかと思いきや、“カーボンフリー”と見なされる合成燃料だったり、水素を燃料にしたり……、と道筋がまったく残されていないわけではない。
理論上、水から作ることができる水素を燃料に用いる燃料電池車が理想像のように思えるが、まだ水素の生成方法や水素ステーションのインフラには課題が残っている、と言わざるを得まい。水があるところであればどこでも生成することができる、石油のための争いがなくなる、という観点から“平和の燃料”としてもてはやされた時期もあるのだが……。