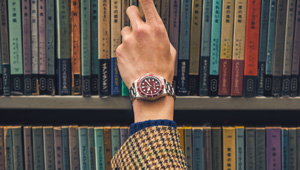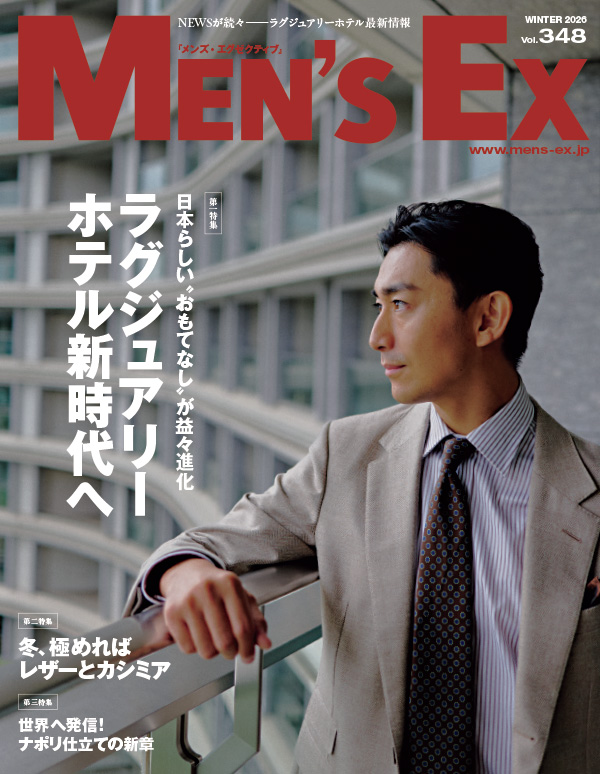“プラグイン”はエンジン車? それとも電気自動車?
先日、欧米の自動車市場について調べていたところ、実に興味深い事実に出くわした。日本とは異なり、アメリカやヨーロッパの統計では、純粋な電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHEV)を“プラグイン車”としてひとくくりにしているケースが大半を占めていたのだ。
エンジンを積んでいないEVとエンジンを積んでいるPHEV。日本では別カテゴリーのクルマとして厳格に区別している。それとは好対照を成すこうした状況は、どうして生まれたのだろうか?
その答えは、文字どおり“プラグイン”という言葉にある。
プラグインとは、自宅の電源コンセントや公共の充電施設などと車両を「接続する」ことを意味する。要は、外部から電気エネルギーを受け入れられる自動車はすべてプラグイン車なのである。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの内燃機関を積んだPHEVであっても、充電した電力で走れるので走行中にCO2を排出せず、地球温暖化現象を減速させることにつながるというわけだ。
つまりPHEVも使い方次第ではEVと同じくらい環境に優しいクルマになりうるのだ。こうして考えると、欧米でEVとPHEVがプラグイン車とひとまとめに呼ばれていることも理にかなっているように思えてくる。そんな中、注目したいのが北欧の自動車メーカー、ボルボの動向だ。