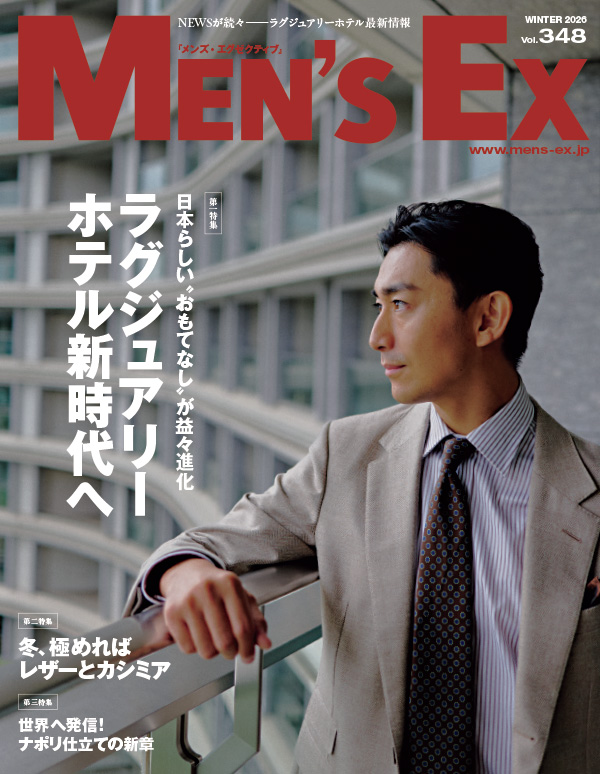発酵食の概念を覆す独創的な料理
玄関で靴を脱いで畳にあがる。日本の生活文化を継承する“日本旅館”でありながら、ホテルに匹敵する快適性を備えた「星のや東京」は、その在り方と同様に、開業時から革新的な食体験を提供してきた。
料理長の浜田統之氏はフランス料理の国際コンクールで何度となく好成績を収めた凄腕。その料理は「Nipponキュイジーヌ」と称され、日本の食材の魅力を丁寧に伝えてきた。

そんな「Nipponキュイジーヌ」が2020年の夏から日本の発酵食品を用いた「Nipponキュイジーヌ ~発酵~」に進化し、11月30日までは秋メニューが提供されている。
その内容が実に魅惑的なので、何はさておき一部をお目にかけよう。

魚介類に米飯、米麹、塩を混ぜて乳酸発酵させた滋賀県の郷土食「熟鮓」を、フロマージュブランとソーテルヌワインのジュレを合わせることで再構築。熟鮓には独特の酸味と臭みがあり、実を言うと筆者は今まで苦手としてきたのだが、これを口にした瞬間、思わず目尻が下がった。酸味と甘みのバランスが秀逸で、香りがふくよか。心がほぐれ、後に続く料理への期待がぐっと高まった。

五味(酸・塩・苦・辛・甘)をそれぞれ一口サイズの料理で表現する浜田料理長のスペシャリテ「五つの意思」に発酵食品をプラス。“酸”をテーマにした「しめ鯖のルーロー」には田舎漬けたくわん、“塩”をテーマにした「ボルシチ」には金山寺味噌といった具合。発酵食ならではの深い旨みが料理の味わいに奥行きを与えていて、少量ながら日本の食が豊かであるとしみじみ感じさせてくれる。

塩麹でマリネした金目鯛を、ぬか漬けにした舞茸などとともに発酵バターを使ったパイ生地で包んで焼き上げた一品。ベアルネーズソースにはエシャロットのぬか漬け、付け合わせのサラダには古くから禅寺で保存食として作られてきた大徳寺納豆を用いている。

ローストした鹿のロース肉に鹿の出汁を使ったコンソメスープを合わせたメインディッシュ。徳島県で古くから作られている豆味噌の一種「ねさし味噌」が鹿肉の旨みと渾然一体となり、深い余韻がもたらされる。
聞けば、浜田料理長にとっても特に思い入れのある一皿とのこと。「猟に同行した際、目の前で鹿が罠で捕らえられ、さばかれるところを見るという貴重な経験をしました。猟師の方が、罠にかかった鹿を強打する際に『おまえの命は絶対に無駄にしないからな!』と大声で叫ぶ様子や、鹿が絶命した後に手早く血抜きし、皮や肉を処理している場面が強烈に印象に残っています。改めて、料理人は魚や動物、植物などの命を預かっていることを実感し、食材を無駄にしてはいけないという思いが強くなりました」(浜田料理長)。
そもそも、浜田料理長が発酵食品をコースのすべての料理に取り入れたのはなぜなのか。それは「体の内側から健康になってもらいたい」という想いからだった。そして、そこには、長野県軽井沢町のフレンチレストラン「ブレストンコート ユカワタン」の料理長を務めていた頃の“実体験”が活きている。
「発酵の力に着目するようになったのは、当時、発酵食材を餌として食べている家畜が元気いっぱいだったのを見たから。酵母菌を食べて育った豚は内臓が強くなりました。内臓が強くなると、糞が臭くなくなり、体の内側から健康になった結果、肉の臭みがなくなりました。また、チーズを餌にしていた地鶏は内臓が強くなったおかげで暑さに耐えられるようになりました。そうしたことを踏まえ、今回、コロナ禍における新たなコースを考えるにあたり、免疫力アップのために発酵食材を取り入れようと考えたのです」(浜田料理長)
たしかにヒトの免疫細胞の約6割は腸に存在していると聞く。そのため、善玉菌を含む発酵食品を食事に取り入れて腸内環境を整えれば免疫力が高まるのも頷ける。また、浜田料理長は「ただ健康に良いだけではなく、それぞれの食材の旨みを爆発的に上げ、美味しく召し上がっていただくためにも発酵食材をうまく取り入れたい」と考えた。それゆえに、理性で味わうのではなく、素直に美味しいと感じられるコース料理に仕上がっているのだ。