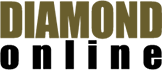仕事の効率化、「働き方改革」よりも「社員の幸せ」が大事

世界で「勤勉」「働き者」と評価される日本人だが、その労働生産性は低い。その理由はストレスと、長時間・非効率な労働環境にあると慶應義塾大学大学院教授の前野隆司氏は指摘する。前野氏が提案する、これからの組織のあり方とは。
※本稿は前野隆司『幸せな職場の経営学 「働きたくてたまらないチーム」の作り方』(小学館)の一部を再編集したものです。
勤勉で働き者の日本人は、労働生産性が低い
平成29(2017)年「労働安全衛生調査(実態調査)」(厚生労働省)によると、「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄がある労働者」の割合は58.3%。職業人口の半数以上が、何かしらのストレスを感じているのです。
そして、2016年のマンパワーグループの調査によると、職場におけるストレスの原因の1位は「上司・人間関係」でした。
また、「時間あたりの労働生産性と労働時間」について世界と比較してみると、OECD(経済協力開発機構)のデータ(2017年)に基づく日本の時間あたりの労働生産性は47.5ドルで、OECD加盟国(36カ国)中20位です。就業者1人あたりの労働生産性は84.0ドルで、36カ国中21位です。かなり低い値を示しています。
これらのことから、世界的に見ても「勤勉」で「働き者」であるはずの日本人が、実は労働生産性という観点から見ると、非効率的な働き方をしていることは明らかです。前述のストレス強度も鑑みると、日本の労働人口のうちおよそ半数以上の人が、人間関係などのストレスを感じながら、長時間、非効率な労働を強いられているということになります。
勤勉で働き者の日本人は、労働生産性が低い
政府主導の「働き方改革」は、GDP(国内総生産)を増やすため、社会的マイノリティとされる女性や障がい者を積極的に雇用し、インクルーシブ(包括的)な組織を目指すこと、過重労働によってもたらされる精神的苦痛を軽減させることを目的としています。
しかし、「時短だ! ダイバーシティだ! さあ、やってみよう」などとスローガンだけを与えられても、多くの現場では実際に何をしたらいいかわからず、戸惑うことになりがちです。私も働き方改革の考え方自体には共感しますが、ウェルビーイング(幸せ)に関連づける余地はまだまだ残されていると感じます。
高度経済成長期に代表されるトップダウン型組織運営がうまく機能していた時代には、こうした通達も受け入れられたかもしれません。しかし、時代は変わりました。スピーディーにテクノロジーが進化し、それに伴って人々の意識もどんどん変化しています。誰もが、もはや古いパラダイムには限界を感じ始めているのです。それなのに、国のトップも企業のトップも、トップダウン方式で物ごとを決め、働く人々を管理しようとしていたら、イノベーションは起きません。抜本的な改革のためには、職場の雰囲気や組織体系を変えるのみならず、理念レベルでの変革を行うことが必要なのです。
「幸福学の父」とも称される米イリノイ大学心理学部名誉教授、エド・ディーナーらの論文によると、主観的幸福度の高い人はそうでない人に比べて創造性は3倍、生産性は31%、売り上げは37%高い傾向にあります。また幸福度の高い人は職場において良好な人間関係を構築しており、転職率・離職率・欠勤率はいずれも低いという研究データもあります。
さらに、米カリフォルニア大学のソニア・リュボミアスキー教授も、「幸せな社員は、不幸せな社員より生産性が1.3倍高い」という調査結果を出しています。国内でも、日立製作所の矢野和男さんの研究をはじめ、幸せであることは生産性を30%ほど増やすという調査結果が続々と発表されています。
だからこそ、これからの企業や組織は「働き方改革」で時短を徹底して無駄を減らすことを考えるのではなく、まず「社員やチームメンバーを幸せにすること」を目指すべきでしょう。創造性が3倍、生産性が1.3倍になれば、結果的に時短にもつながるはずです。
「幸せに働いていない」と気づかないことこそが社会問題
ところが、トップダウンによる働き方改革で現場の当事者たちが「やらされ感」を感じれば、人々が幸せになるためにある4つの因子のうち1つである「やってみよう!」因子(自己実現や成長を実感することで幸せを感じられる因子)が低くなります。幸福度が低くなれば、結果的に生産性や創造性が下がる可能性も高くなるため、結局、「働き方改革」の成果が出ないという悪循環に陥ります。この点が今の大きな課題の一つではないでしょうか。
そもそも、仕事というものは労働であって「対価=賃金」を得るために自分の人生や時間を差し出すものである、という従来からの構図に、私たちは囚れ過ぎてはいないでしょうか。そのような労働契約説的な考え方は、個人の幸福を考慮していません。メンタルの状態を考慮せずに仕事を続けていると、ブラック企業体質は当たり前になり、いずれ心身の病になってしまうリスクがあります。つまり自分たちが「幸せに働いていない」ことに気づけていない人がいるという事実そのものが、大きな社会課題なのです。
当然のことですが、雇用される側だけでなく、雇用する側の考え方も変えていかなければなりません。
集団主義から個人主義に移る日本の経営スタイル
実は、旧式の日本型経営、すなわち終身雇用や年功序列などに代表される制度が整っていた「集団主義的な経営スタイル」は、安心感という観点ではよくできた仕組みでした。ところがその後、欧米型の成果主義、つまり「個人主義的な経営スタイル」が採用されるようになると、経済的にはもちろん、意識面でも格差が広がりました。そしてさらに追い討ちをかけるように、企業の合併や買収、そしてリストラが横行するようになったのです。
ここで、「個人主義」と「集団主義」という用語について説明しておきましょう。これらは心理学をベースに、文化間の比較を行う文化心理学の用語です。
個人主義とは、個人の独立や権利を重視する考え方。集団主義は、個人の独立や権利よりも、集団としての価値を重視する考え方です。
統計分析の結果、大ざっぱに言えば、欧米は個人主義的、アジアは集団主義的な社会であることが知られています。
ただし、世界を西洋と東洋に分けるステレオタイプの議論には注意が必要です。アメリカにも集団主義的な人はいますし、東南アジアにも個人主義的な人はいます。本稿では、わかりやすくするために、あえて個人主義と集団主義という言葉を使います。同様に、「東洋」と「西洋」という言葉も注意が必要です。こちらについても、あえて単純化して議論を行います。
8割の人のモチベーションが下がる、日本の個人主義
さて、いわゆる個人主義や成果主義は、アメリカのように「転職=キャリアアップ」という文化が強く根づいている国ではうまくいきます。一方、日本のように転職がまだ一般的でない社会に取り入れたとき、トップの2割程度の人たちにはやる気が出て良い影響がありますが、残り8割程度の人にとっては、モチベーションダウンへとつながり、残念な結果となりかねないのです。
集団主義と個人主義、どちらにもメリットとデメリットはあります。仕事のパフォーマンスが高い人に報いるべきなのか、そうでない人も含めて皆が幸せに生きるべきか。どの価値を重視するかによって答えが異なる、難しい問題です。
繰り返しになりますが、昔の日本企業の経営は集団主義的でした。その後、バブル崩壊とともに合理化、効率化が重視された結果、長時間労働やそこから引き起こされる過労死、うつ病などのさまざまな問題が湧き上がってきました。そして最近はティール組織やホラクラシー組織といったあり方が注目を浴びています。
一人ひとりが主体性を持つティール組織
ここで、本書にも何度か登場している「ティール組織」と「ホラクラシー組織」についても簡単にご紹介しましょう。「ティール(Teal)」とは、フレデリック・ラルーの著書『ティール組織』(英治出版)に由来します。
タイトルにある「ティール」とは、「青緑」という色を表す単語です。同書では時代とともに進化する組織形態を色にたとえ、発達段階に伴って表しています。最初の形態は「衝動型組織」=赤、続いて「順応型組織」=琥珀、「達成型組織」=オレンジ、「多元型組織」=緑というように、その発達具合に従って色が変化していくのです。「青緑(ティール)」は発達の進んだ組織形態である「進化型組織」を示します。
著者のラルーによると、進化型組織には従来のようなピラミッド型の組織構造は見られません。社員一人ひとりが主体性を持ち、意思決定ができる自主経営組織です。指揮命令系統もなく、従来の雇用契約を超えた、「信頼」でつながり合う生命体のような組織形態なのです。
よりフラットな体制のホラクラシー組織
他方、「ホラクラシー(Holacracy)」は、2007年にアメリカの起業家ブライアン・J・ロバートソンが提案したマネジメントシステムです。
ティール組織と多くの共通点がありますが、中央集権型・ピラミッド型のヒエラルキーが形成される管理システムを一切排除し、よりフラットな組織体制であるチームやサークルによって組織が成り立つ仕組みです。こうしたホラクラシー型の組織では、上司は存在せず、決済の滞りや責任のなすりつけ合い、派閥争いといった複雑な人間関係がなくなり、関わる誰もが主体的に考えて行動することで、生産性の向上や、イノベーションの創出が期待できます。
アメリカのZappos.com(以下、ザッポス)などの企業は、ホラクラシー的な経営を実践する代表的な例として、今、大きく注目されています。
ザッポスは靴やアパレルを扱うオンライン小売企業ですが、存続の危機に瀕していた同社はホラクラシー経営によって見事に復活。年商1200億円という業績を実現させ、大成功をおさめたことで一躍、有名になりました。同社は「DeliveringHappiness(デリバリング・ハピネス=幸せを運ぶ)」を経営理念に掲げて顧客と社員の幸せを第一に考えるという斬新なマネジメント手法を生み出し、フォーチュン誌の「もっとも働きがいのある企業100社」に数年にわたってランキングされたのです。2009年にはアマゾンが9億4000万ドルで買収したことも話題になりました。
これからの時代に求められる組織
顧客と社員の幸せを第一に考えるということは、一見、真逆の価値観のように思えますが、実は驚くことに、ティール組織もホラクラシー組織も昔の集団主義的・家族経営的だった頃の日本企業の方法に似ている部分が少なくありません。まったく新しいようで、実際には新しいものと古いものを融合させた考え方と言うべきではないかと思います。
私はこれまで、経営面においても、社員との信頼関係においても、そのどちらもうまくいっている企業をいくつも見てきました。また、経営学のみならず、哲学の歴史やシステム論の歴史についても俯瞰(ふかん)的に見てきました。
これらを統合して捉えると、これからの時代に求められる組織とは、集団主義の良さも個人主義の良さも兼ね備えた組織、つまり「ウェルビーイングな組織」であると考えています。個人か集団に偏るのではなく、「個人の幸せ」と「皆の幸せ」のどちらも大切にするのがウェルビーイング第一主義です。幸せファースト。皆の幸せを第一に、です。
そのためには、西洋と東洋どちらの叡智が優れているかを争っている場合ではありません。両者の良い面を融合させ、ハイブリットな新しい概念を創り上げるべきです。
ウェルビーイング第一主義は決して難しいものではありません。自分も含めた「皆の幸せ」をまず考えることです。この、「皆が幸せになるべきである」という当たり前の考えを中心に据えることによって、ティール組織やホラクラシー組織といった新しい考え方と、家族経営のような古き良き考え方の類似性を統一的に捉えることが可能になるのです。
前野隆司(まえの・たかし) 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授
1962年山口生まれ。広島育ち。84年東工大卒。86年東工大修士課程修了。キヤノン、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授等を経て、2008年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科教授。2011年より同研究科委員長兼任。2017年より慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼任。