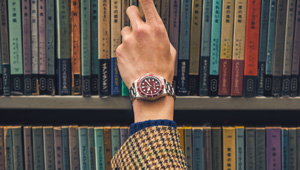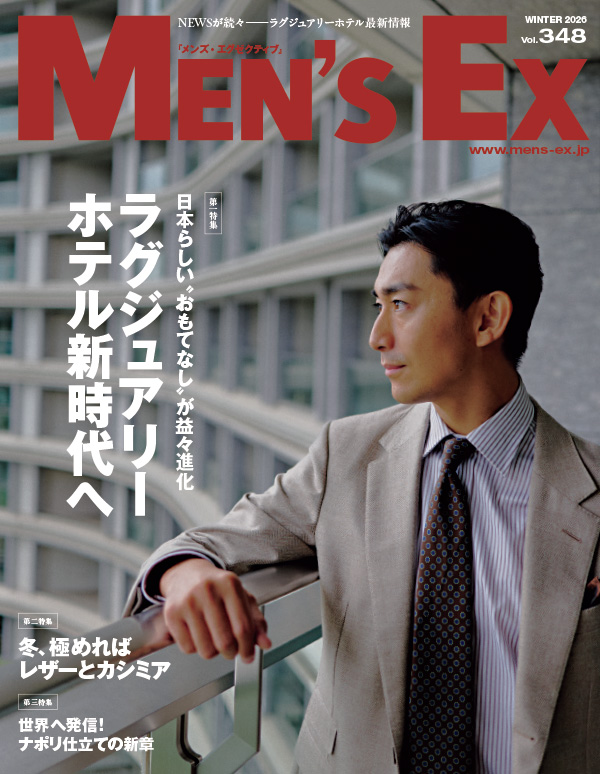東京女子医科大学・野中康一教授に教わる
自分の未来を守る健康への投資術
働き盛りの壮年期はがんに罹患するリスクも跳ね上がる。しかし、早期に発見して治療すれば恐れることはない。その手段として消化器がんには内視鏡検査が最も有効だ。

東京女子医科大学
野中康一(のなか・こういち)教授
1976年、熊本県生まれ。医学博士。2002年、島根医科大学(現・島根大学)医学部卒業後、熊本大学医学部第一内科(消化器内科)に入局。NTT東日本関東病院、埼玉医科大学国際医療センターなどを経て、‘20年より東京女子医科大学消化器内視鏡科教授。
早期発見を目的とするなら内視鏡検査が最も高精度
国が推奨する大腸がん検診では便潜血検査が行われている。胃がん検診では、胃内視鏡検査または胃部Ⅹ線(バリウム)検査のいずれか一つを受診者が選択できるようになっている。「しかし、がんの早期発見を目的とするなら便潜血検査や胃部Ⅹ線検査では不十分です。なぜなら、これらの検査の精度は決して高くないからです」と野中先生は指摘する。
例えば、便潜血検査で進行大腸がんを検出する感度は(便の採取が)1日法で73.3%、2日法で85.6%という研究論文があり、感度95%以上の大腸内視鏡検査に比べると検出精度はかなり劣る。しかも早期がんではさらに感度が低くなるといわれている。同様に胃部X線検査の感度も70~80%で、進行がんの段階で見つかることが多いという。

「消化器がんの早期発見には内視鏡検査が最も有効です。自覚症状のない人が定期的に内視鏡検査を受けていれば、がんが粘膜内にとどまっている早期の段階で発見し、その場で内視鏡を使って切除することも可能です。大腸がんや胃がんで亡くなることはまずありません」と野中先生は断言する。さらに咽頭がんや食道がんを同時にチェックできるのも内視鏡検査を受ける大きなメリットといえる。
消化器がんの内視鏡検査はどのくらいの頻度が適切か
では、消化器がんの内視鏡検査は、どのくらいの頻度で受ければよいのだろうか。「2020年に発表された日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは、大腸内視鏡検査で異常が見つからなかったときは5年後をめどに次の内視鏡検査を受けることを提案しています。ただし、年齢や家族歴、ライフスタイルなどで罹患リスクは変わってくるため、検査してくれた医師の指示に従うのがよいでしょう」と野中先生はアドバイスする。
一方、胃内視鏡検査では、ピロリ菌に感染している場合、定期的な内視鏡検査が推奨されており、1~2年間隔で内視鏡検査を受けるのがよいと考えられている(国が推奨する胃がん検診は2年に1回と決められている)。また、注意したいのはピロリ菌を除菌した人だ。除菌が成功すると胃がんの罹患リスクは3分の1に減るといわれ、安心して胃がん検診を受けない人が多い。
「しかし、ゼロになったわけではありません。萎縮性胃炎や腸上皮化生がある場合はより注意が必要で、医師の指示に従い、定期的に内視鏡検査を受けることが大切です」と忠告も。
消化器がんの検診ポイント
男性の罹患率・死亡率ともに上位を占める大腸がん、胃がん、食道がん。その特徴と内視鏡検査の頻度を知り、今後の検診行動に生かそう。
【大腸がん】
●特徴
大腸がんの罹患者数は、食事の欧米化などに伴い、年々増加している。女性が罹患するがんの第1位、男性では第2位だが、罹患者数は男性のほうが多く、女性の1.3倍とされている。飲酒などの習慣がある方、肥満、家族歴がある方は注意が必要だ。早期では症状がほとんどなく、血便や排便習慣の変化(下痢、便秘)、便が細くなる、残便感などの自覚症状が現われたときは進行していることが多い。そのため死亡者数も増えている。飲酒などの習慣がある方、肥満、家族歴(家族性大腸腺腫症、リンチ症候群の家系)がある方は注意が必要だ。
●内視鏡検査の頻度
日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは、大腸内視鏡検査で異常がなかった場合は5年後、10個以上のポリープまたは20mm以上の大きなポリープを切除した人は1年後、それ以外(小さなポリープがあるなど)の場合は3年後の大腸内視鏡検査が推奨されている。
【胃がん】
●特徴
胃がんの罹患者数は近年減少傾向だが、死亡者数はそれほど減っていない。罹患者数は男性のほうが多く、女性の2.2倍である。早期では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合もある。ピロリ菌に感染している、または感染したことがある方、食塩・高塩分食品の摂取が多い方などは罹患のリスクが高い。代表的な症状は胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振だが、胃炎や胃潰瘍でも起こる症状なので、放置されて発見が遅れることも少なくない。
●内視鏡検査の頻度
ガイドラインなどで推奨されている受診頻度はない。ピロリ菌に感染している場合は1~2年間隔、除菌後に萎縮性胃炎や腸上皮化生がある場合も同様に胃内視鏡検査を受けるのがよいと考えられている。国が推奨している胃がん検診は2年に1回と定められている。
【食道がん】
●特徴
食道がんの罹患者数は年々増加している半面、死亡者数は横ばい傾向だ。罹患者数は男性のほうが圧倒的に多く、女性の4.5倍である。早期では自覚症状がほとんどなく、がんが進行するに従って飲食時の胸の違和感(胸の奥がチクチク痛む、熱いものを飲み込んだときにしみる感じ)、飲食物がつかえる感じ、体重減少、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が出てくる。なお、飲酒すると顔が真っ赤になる方や熱いものをよく好んで食べるなどの習慣がある方は要注意だ。
●内視鏡検査の頻度
胃がん検診(胃内視鏡検査)の中で食道がんの有無をチェックすることになるので、2年に1回のことが多い。しかし、食道がんは早期の段階で転移しやすいという特徴がある。早期発見のためには、少なくとも年に1回、ハイリスクの自覚がある人は半年に1回は内視鏡検査を受けることが望ましい。
内視鏡検査の普及に伴い、よい施設を見分ける時代へ
「ほかの検査方法よりもがんの検出精度が高いといっても大腸内視鏡検査では、10~20%の見逃しがあると報告されています」と野中先生は打ち明ける。がんの見逃し率を少しでも減らすために各医療機器メーカーは検査支援システムなどを開発し、内視鏡検査機器に搭載してきた。
「例えば、検査支援モードに切り替えるボタンを押すだけで、がんの疑いがある部分が茶色に映る内視鏡検査機器が普及し、がんの検出率はかなり上がりました。この技術が開発される以前は検出率がたった5%だった咽頭がんが今では100%近くが発見されるようになったとの報告もあります」と野中先生は説明する。近年ではAI(人工知能)の診断サポート技術の応用も始まっている。
一方、日本消化器内視鏡学会によると、胃がん検診の検査項目に内視鏡検査が追加されたことで、この検査を導入する健診センターや病院、クリニックが急増しているという。
「数の増加に比例して施設間の実力格差が開いてきており、早期がんを確実に見つけ、根治するにはどこの施設で内視鏡検査を受けるのかということが重要になっています。この検査は自費診療ですし、よい施設の見分け方を知っておくことが肝心です」と野中先生はアドバイスする。
【Q&A】教えて野中教授!
検査を受ける人の「苦しい」「つらい」を減らすために導入された新しい技術や工夫を中心に内視鏡検査の素朴な疑問に答えていただく。
Q. 鼻からカメラを入れる経鼻内視鏡検査のほうが楽?発見率は低い?
A. 経鼻内視鏡検査のメリットは、口からカメラを入れる経口内視鏡検査と比べて嘔吐反射が非常に少ないことです。ある程度、操作の上手な医師が行えば、オエッとえずくような苦しさはありません。また、高画質の小型カメラが搭載された検査機器が普及し、がんの見逃し率は経口内視鏡検査とほとんど変わりません。
Q. 鎮静剤を利用するのはNG?
A. 意識が下がる鎮静剤を使うメリットは、処置中の苦痛や不安の軽減、安静の維持が挙げられます。胃内視鏡検査で鎮静剤を使用する施設が6割以上を占めるというデータもあり、今や受診者の選択肢の一つになりつつあります。一方でデメリットは、血圧低下や呼吸抑制などをきたす可能性があることです。また、当日は車、バイク、自転車の運転はできません。
Q. AIのサポートがあるほうが発見率は上がる?
A. 内視鏡検査でもAI(人工知能)に検出パターンを学習させて診断サポートに役立てる技術を導入してます。検出パターンが限定的な大腸がんは、エキスパートとほぼ同程度の発見率でがんを検出できるといわれます。一方、検出パターンが複雑な胃がんはAI活用に至らず、人間の診断力に頼らざるを得ない面がまだ大きいです。
[MEN’S EX Winter 2025の記事を再構成]