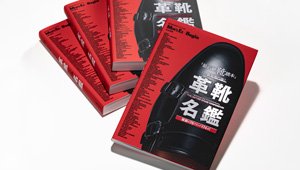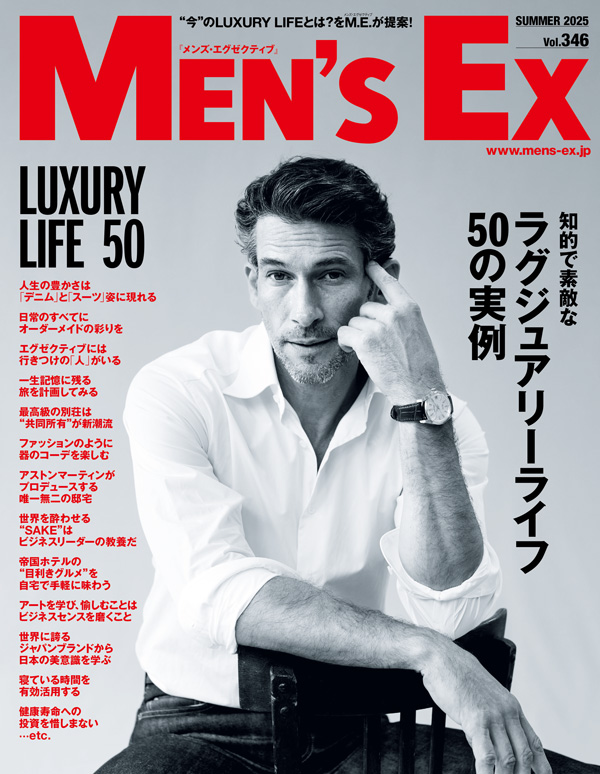この流れは、そもそもSUVシリーズ、たとえばCX-3をサンではなくスリーと読んでいたことから、昨年秋にデビューしたCX-30をサーティと読み、そして、今に至っているのではないか、と、個人的には勝手分析している。いずれにしても思うのは、最新のマツダ車に対して、そう読まねば失礼に当たるのではないか、そんな意識が自分の中のどこかにあることだ。
志高いコンセプトモデルを現実のものに
と、ヨタ話が続いたが、個人的にそれほどまでに一目置いているモデルが、このマツダ3だ。2017年の東京モーターショーで「魁(KAI)CONCEPT」として発表されていたモデルを覚えているだろうか? あれがマツダ3のコンセプトカーだった。
あの時は、同時に発表された「VISION COUPE」とともに「え?これ市販するの?」と驚愕し、マツダブースに釘付けとなってしまっていた。実は、マツダは市販モデルへと繋がらないコンセプトカーは作らないと明言しており、特に「魁 CONCEPT」に対しては、斬新だけど乗降性に不足をイメージしてしまうリア回りの造形や、風景をボディへと写し込み一体化させるというデザイン手法に共感を覚えながらも、あまりに理想を掲げすぎてやしないかと、も思った。

しかし、マツダは、同じように理想を高く掲げたスカイアクティブXというパワーユニットとともに、昨年5月にマツダ3をデビューさせてしまった。スカイアクティブX搭載モデルについては、より理想を極めるという意味合いから改良を続け昨年末の発売となったが、まさか、本当に、あのコンセプトのままにデビューするとは思っていなかったので、デビューの衝撃たるや凄いものがあった。
もちろん、これがスーパーカークラスであったならば理解はできる。しかし、マツダ3はマツダとしてはど真ん中の商品、つまり、売れ筋とならねばならないという使命を背負っており、たとえ目標を高く掲げようとも、失敗は許されないモデルだ。それでも、ほかブランドとは異なる個性を追求し、それ具現化してしまった。最近のマツダはブレがないという意味合いでも、マツダ3はCX-30とともにその骨頂だ。それゆえに、筆者の周囲でも評価はすこぶる高い。
大排気量ともディーゼルとも異なる、新鮮なフィーリング

スタイルは、従来のハッチバック的なスタンスにあるファストバック、そしてセダンを設定。ボディサイズは、ファストバックは全長4460mm、全幅1795mmと、日本でコンパクトと呼べるギリギリだが、ライバルであるVWゴルフが属するCセグメントモデルとしては標準的なサイズ感にある。
デザインは、マツダのデザインコンセプト“魂動デザイン”をさらに“深化”させた。それは、単なる鉄の塊ではなく、人とクルマをエモーションにつなぐためのデザインを意味し、マツダ3では控えめでありながら豊かな美しさを表現したのだという。フェンダーラインをなぞる以外に見当たらないサイドのキャラクターライン、不要を取り除くというシンプルな塊感、光の映り込みをも取り込むという手法によって、このクラスとしてはあり得ない造形を実現。リアへと流れ落ちていくルーフラインは美しいに尽きるし、ファストバックという言葉遣いにも納得できる。
しかし、実際には、つまり実用性という面では、先に筆者が感じたリアシートへの乗り込みへの不足については、やはり頭を屈めねばならない。リアシートにおける居住性も適度なタイト感が心地よさを生んでいることは確かだが、表現を変えると、囲まれ感は強く、ブラック内装も加わって、閉じこめられた感を覚える人もいるやもしれない。また、チャイルドシートを取り付けた際に、果たして子供を乗せやすいのか、といった疑問も湧いた。
走りについては、スカイアクティブXがもたらす、新しいフィーリングはやはり驚きだ。このシステムについて詳しく解説するとこれだけで終わってしまうのでここでは簡潔に述べるが、これはディーゼルエンジンの熱交換効率の良さ、つまり優れた環境・燃費性能と、ガソリンエンジンのレスポンスや高回転までの伸びといった、両エンジンの良さを合わせ持ったユニット。
システムとしては、混合気を燃焼させる際に、ガソリンエンジンでは着火にはプラグのみを用いていたが、そこにディーゼルエンジンで用いられる圧縮着火を組み合わせたSPCCI(火花点火制御圧縮着火)によって実現している。モーターを駆動力としたEVへ移行しようとしているこの時代に、内燃機関にはまだまだできることがあるとマツダがこだわった技術であり、そこにもマツダの理想を追求するスタンスがある。
そのフィーリングは、発進時からはっきりと感じ取れる。アイドリングストップからの発進には、従来のキュルルンという音と振動を奏でるスターターモーターではなく、ISG(ベルト式インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター)を採用したことで、音、振動ともに感じさせぬままに発進。直後に豊かなトルクを低回転域から立ち上がり、ATの存在を感じさせないようにとISGのアシストを上手く利用しながらシフトアップを繰り返し、高回転へとスーッとそして力強く伸びて行く。その仕立ては、大排気量ガソリンエンジンとも異なる、かといってディーゼルエンジンとも異なる、フィーリングはまさに新鮮。乗り込んで行くうちに何よりも扱いやすさがあり、それがスポーティさを表現していることに気付く。快適性や扱いやすさといった面ではマイナスに作用するフィーリングを、あえて作り込まなかったのだろう。