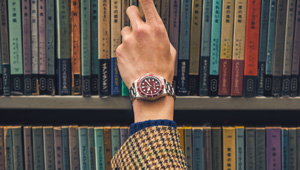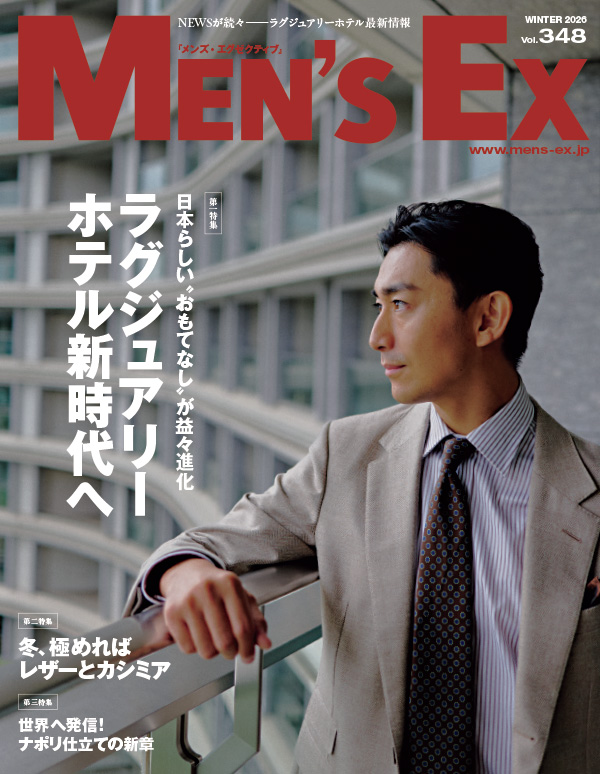お能と聞いて皆さんは何を思い浮かべるだろうか。多くの方は「能面」をイメージされるかもしれない。一方で「何を言っているのか聞き取れない」や「眠くなる……」という印象をお持ちの方もいれば、そもそも、能を見たことがない、能楽堂に行ったことがないという方もいるだろう。
もっと気軽に能楽堂に足を運んでもらえる公演ができないか――。20年前、そんな思いと挑戦を胸に抱いた若き能楽師がいる。喜多流シテ方能楽師の塩津圭介さんだ。そして、「若者の、若者による、若者のためのお能」を掲げ、大学生だった塩津さんが学生の仲間とともに立ち上げた能公演が「若者能」だった。
40歳でも若手と呼ばれる能楽界にあって、20歳そこそこの能楽師が公演を立ち上げるなど、当時は異例中の異例のことだった。「お能は二十歳になるまえから。」というキャッチコピーを掲げ、今年で「若者能」は20周年を迎える。今なお、現役の大学生が中心となり運営している「若者能」への思い、そして能楽の魅力を塩津さんに伺った。

能楽シテ方喜多流。1984年生、東京都出身。喜多流能楽師・塩津哲生の長男。3歳のときに独吟「老松」にて初舞台。父に師事。2011年「猩々乱」、2015年「道成寺」、2018年「石橋(赤獅子)」を披く。APU立命館アジア太平洋大学非常勤講師。2004年に若者の若者による能「若者能」を立ち上げ毎年公演を開催している。
M.E. 今年、「若者能」が20周年を迎えられるとのこと。まずはおめでとうございます。そもそも「若者能」は20年前、どのような経緯で立ち上げられたのでしょうか?
塩津 第1回は私が大学2年生の時でした。小中高と一緒だった友人が何名かいて、それぞれが将来は家業を背負うという似た境遇を持っていました。彼らとなにか自分たちで始めたいよねという話をしていて、せっかくなら、お能の公演やってみたら面白いんじゃない?というところからスタートしました。自分たちでチラシを作って、コピーして、配って、番組表を手書きで作り……。第1回公演は完全に手弁当でしたね。その様子を見ていてくださった虎屋の黒川光博社長(現会長)から、せっかくだから、ちゃんとした組織を作って運営したらよいと勧められて、第2回公演に向けて大学生仲間が主体となって「若者能実行委員会」を立ち上げたのです。以来、学生さんたちが代々、実行委員を引き継いで、企画、運営、広報など頑張ってくれています。
M.E. まさに、若者の、若者たちによる、若者のための能公演ですね。「若者能」は当時としてはかなり斬新な企画、上演もあったとか?
塩津 確かに能楽業界にアンチテーゼを投げかけた感はありますね。縦書きが慣例だったチラシのフォーマットを横書きにして、初めて見る人でも分かりやすくしたり、未就学児の入場をOKにしたり。
M.E. 能面をかたどったチラシも作ったそうですね?
塩津 あれは怒られました。能楽師にとって命ともいうべき「面(能面)」をチラシにかたどるなんて!と(苦笑)。それからプログラムに漫画の解説を載せたり、Twitter(現X)やLINEを使った解説同時配信を行ったりしました。今でこそ公演前に演者が舞台に出て、解説することは当たり前のように行われていますが、当時は紋付きを着た役者が舞台上で喋るなんてとんでもない!という時代でしたね。
M.E. 解説の同時配信は今でも続けておられますね。でも絶対にそうしていただいたほうが、見ている側は分かりやすいと思います。この20年、随分とチャレンジを続けてこられたことが伝わってきます。
塩津 そうですね。諸先輩方が大切に守ってこられたことは今も大事にしていますが、一方で新しいことを取り入れたことで、最初にお能を見るなら「若者能」があるよね、といっていただけるようになったことは大きいと思います。友人が実行委員をしているからというのをきっかけに学生さん同士が誘い合って能楽堂に来てくださるケースも珍しくありません。能楽堂に初めて足を運ぶ入り口になれたかなとは思っています。
M.E. 入場料1000円という、破格の学生観賞料を設けている点も学生さんにとっては嬉しい点ですね。
塩津 自分でチケットを買って、自分のために能を見に行く、という習慣を持ってほしいと願っています。とはいえ、学生にとってチケット代は決して安くはない。そこで、数年前からは、「応援チケット」というのを作り、社会人の方に個人協賛という形でサポートいただいて、学生向けのチケットを安くしています。
M.E. 3月15日には記念すべき20回目の公演が行われます。20周年というのはやはり感慨深いものがありますか?
塩津 そうですね。第1回のときに産声をあげた子が20年の時を経て、実行委員長を務めてくれている、それだけではなく、かつて実行委員を務めてくれていた子が社会人になって、出世して応援チケットを買ってくれる。やはり文化は皆さんの成長の中にないといけないと感じます。生活も環境もいろいろなことが変化する中で、文化への関わり方も変わっていきます。もちろん、大人の方、40歳の方が60歳になるまで変わらず見に来てくださるというのもありがたいことです。しかし、文化に興味を持つならやっぱり若いうちに一度は触れてもらいたいというのが正直な思いです。
M.E. そういう意味でも「お能は二十歳になるまえから。」というキャッチフレーズが大事なんですね。
塩津 あと、実はこれたばこのキャンペーンのパロディなんですけど、お能はあなたの健康に良い、良い効能を与える可能性がありますよ、というメッセージも隠されています(笑)。若い方はいろいろな意味で柔軟です。ですから、若い時にお能を見るってすごく大事だと思うんです。私も40歳を迎えて、3児の父となり、子育て真っ最中ですが、親子で見に行けるコンテンツって実は少ない。大人向けの公演に子どもを無理やり連れて行っても子どもは退屈するし、子ども向けだとやはり大人はつまらない。ところが、お能は、子ども向けくらいが初心者にはちょうどいい(笑)。今年、上演する『道成寺』だけは、能の中でも特別な曲なので未就学児はNGとさせていただきましたが、また来年以降の公演ではOKにします。子どもにこそ1番のものをちゃんと見せることが大事だと思っています。

M.E. 「若者能」なら親子で楽しめるというのは嬉しいですね。ちなみにもう「若者」じゃないよ!という方でも見に行ってもよいのでしょうか?
塩津 もちろんです。若者にはいろいろな意味が込められています。気持ちが若いとか(笑)。能初心者なら、能に関してはそれはりっぱな若者。いくつになっても誰もが若者的な要素は持っていますから。
M.E. 安心しました(笑)。では、20歳を超えた大人は「能」をどのように楽しめばよいのでしょうか?
塩津 現代に生きるエグゼクティブたちは基本的に非常に忙しい日々を送っているんだと思います。すごくマルチタスクで、一度にいろいろなことを考えて、分刻みで動いている。そんな生活をしている中で、全てから解き放たれる時間を得られるのが能楽堂だと思うんです。
M.E. 確かに一日中何かしら仕事のことを考えて、常に頭がフル回転状態……。
塩津 今の時代って、情報量が多いといわれていますが、それはきっと本来、長時間かけてやることを短時間になるように、中身を圧縮しているからだと思います。だから、能を観ることで、それを逆の流れにしてあげる。なぜなら、能はスローモーションの芸術だからです。能を見ることで人間が本来持っている正常な時間感覚や、物事を処理する速さへと戻してあげる、そうした切り替えの時間にしてもらえればいいなと思います。早く進みすぎてしまった時間の感覚を取り戻して、心に余裕を作る。そうすれば、次また時間軸が速い現実世界に戻ったとしても、心身が対応できるようになるんだと思いますよ。
M.E. なるほど。確かに、能の舞台は時間軸が独特ですね。
塩津 ただし、現代においても、大きな人生のイベントってその方にとってはすごくスローモーションの瞬間になる時があると思うんです。そういう意味では共通した時間軸もあるように思います。
M.E. そうした時間の流れを愉しむのも一つですね。ちなみに、目の前の物語を理解したり能の動きを理解したりする必要はないのでしょうか?
塩津 究極的な言い方をすればそうですね。能を理解する必要は全く無いと思いますし、能という時間感覚の中で、様々なことにその人なりの思いを巡らせる時間にしてもらえればいいのです。お能の上演を見ているこの1時間だけは、自分のためだけの時間。そんな時間にしてもらいたいです。
M.E. 確かに日々の忙しいルーティンの中でふとゆっくり立ち止まる時間をついついおざなりにしがちですね。ゆったりとした時間軸の中で、よく分からないものを観ながら、想像力を働かせて自分と向き合う時間はそうそうないかもしれません。
塩津 現代のエンターテインメントは全部落とし穴が用意されていて、そこにハマると楽しいというストーリーがしっかり作られています。それはそれで見ている側は楽なのですが、能の舞台では自分なりの見方、時間の過ごし方のようなものがあって良いと思います。例えば、今回上演する『道成寺』は、極めて嫉妬心の強い女性の妄執がテーマです。ですが、見ている側としては、様々な見方がある。追いかける女性の立場に立つか、追いかけられる男性の立場に立つか。そもそも執着や嫉妬っていろいろなシーンに当てはまりますよね。自分だったらそうした感情とどう向き合うのか、双方の立場に立って考えられる方は両側に立って考えてみるのもありだと思います。