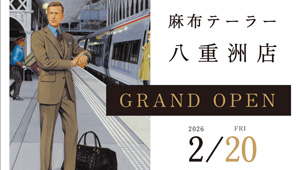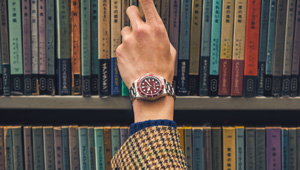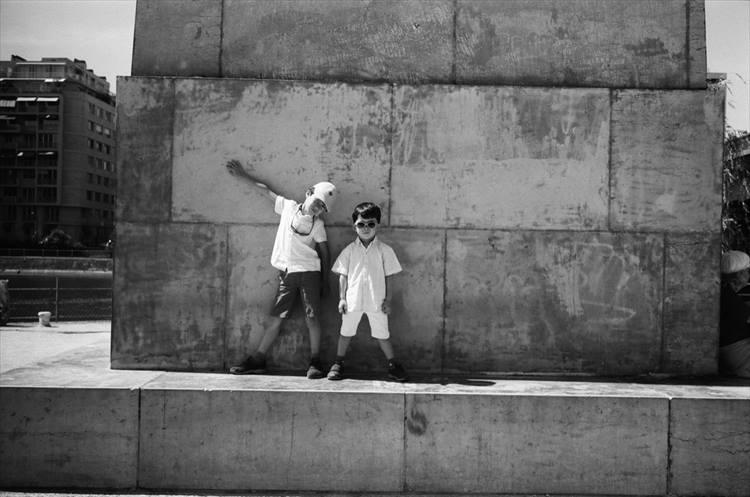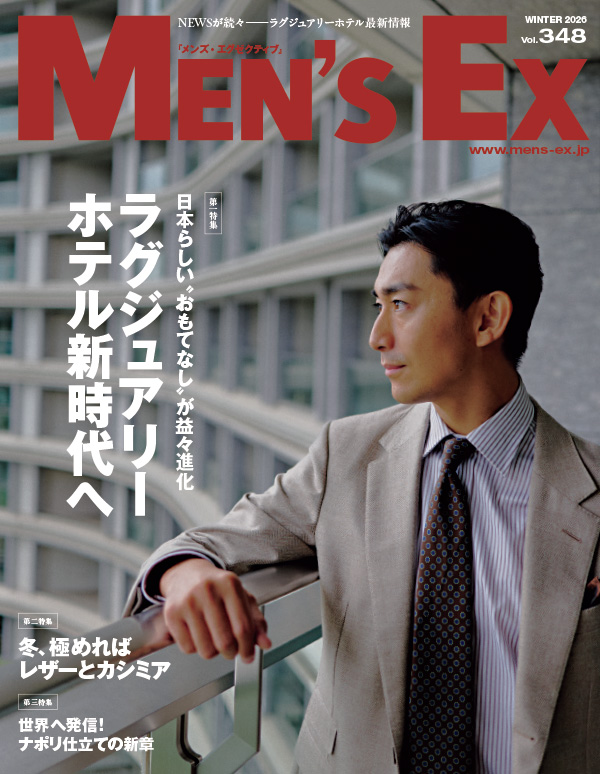カッターの職に飛びつかなかった理由を詳しく教えて下さい
「以前、アルニスで本場の縫いに触れたときに日本との縫い方の違いに大いに驚いたのです。ヨーロッパは階級社会ですので、カッターと縫いの職人とでは立場がまったく異なります。もし自分が縫いの職人にならずにカッターになってしまったら、今後二度と縫いに触れることは出来ないでしょう。カッターにはなりたい。それが自分の目標である。ただ本当に美しい服を作るにはカッティングだけではなく、縫いもしっかり学ばなくてはいけないのでは……と思いました。当時、自分でアタックした別のテーラー、カンプス・ドゥ・ルカからもオファーをいただいていました。こちらは縫いの職人としての雇用です。じっくりと考えた末、いま、縫いを学ばないときっと後悔すると考え、カンプス・ドゥ・ルカで労働許可証を取得していただくことになりました。私のキャリアのスタートでした」。
カンプスでの仕事はどんな様子でしたか?
「人の3倍働きました。最初はベテラン職人のアシスタントとして仕事をするようにと、オーナーから言われました。が、日本にいた時からずっと本物の技術を学びたいと思っていたので、とにかくモチベーションが高かった。仕事ではアシスタントの仕事しか、させてもらえないので、自分の服を仕立てながら核心の知りたかった部分をベテラン職人(パリにおける最初の師匠)から教えてもらっていました」。

「朝早くアトリエに行き、休み時間に自分の服を縫い進め、休憩から戻ってきた師匠に『5分でいいから見て欲しい』とアドバイスをもらう。その夜、自宅に帰り、教わった部分を部分縫いで作り直し、翌朝見せて、またアドバイスをもらう。教わったことは休憩時間に即座に練習し、また見せてといった日々でした。自分はただでさえ出来が悪いのだから、人の3倍はやらなきゃという、若いころのコンプレックスも重なり、24時間、服作りのことだけを考え没頭していました」。
この熱意があったなら上達は早かったでしょうね
「毎朝、オーナーにも見てもらい『もっとこうした方がいい』といったようにアドバイスをもらっていました。最初はアシスタントでしたが、1年経つとメイン(上司と同じ立場)の縫い仕事も与えられるようになり、入社して1年で丸縫いをするメインの職人として仕事をしていました。カンプスでは入社時に、ゆくゆくはカッティングの仕事もさせてもらえる雇用内容でしたので、入社から2年経つと、徐々に裁断やパターンに関わりたいとお願いするようになって。今考えるとなにをそんなに焦っていたのか? と思うほど、1日1日を全力で生きていました。仕事が終わってもアトリエに残り、家でも深夜まで縫っていたので何着も自分のジャケットを縫いあげていましたね」。
その後、仕事に変化はありましたか?
「カッティングに関わらせてほしい、という何度かの押し問答の末、オーナーから『パリにはまだまだ人種差別があるから、アジア人はカッターにはなれない』と言われました。『それならイタリアに行きます』と言ったところ、『イタリアはパリよりも差別が強いんだ。イタリアにも日本人の職人はいるかもしれないけれど、誰一人、カッターとして働いていないだろう』と言われてしまったのです。つまりは『ここで縫いの職人として働いていなさい』と言われているように感じました」。
「これまで、人の何倍も努力することで、すべて実現できたのに、自分のオリジンが原因でカッターになれないとしたら、一体どうしたらいいのだろう……と感じ、言われた言葉が重く心にのしかかりました。同僚とも距離ができて、同時期に父が他界したこともあり、そのころから長らく鬱になりました」。

それは辛いめに遭いましたね……。
「その後、かつてのように、自分自身でもう一度パリのテーラーを回り、カッターに雇用してほしいとチャレンジしました。自分で引いた型紙を持って、数年前と同じようにプレゼンテーションして回る。ですが、自分の型紙を見てくれるテーラーは一軒もありませんでした」。
「鬱状態になっていた自分を奮い立たせましたが、すべてのテーラーからノーと言われて辛かったのを覚えています。自分は求められていないんだなと思いましたね。そうした話を校長先生に相談したら、『差別発言なんて許せない!』と激怒しました。校長先生のお父様が、かつて全世界洋服協会の会長を長く務めていた時代、日本からも多くのテーラーが船で渡仏したそうです。その中でも(お父様が)五十嵐九十九(※)さんを特に応援し、手助けしていたと聞きました」。
※いがらしつくも/パリで学んだ日本人ファッションデザイナー。ピエール・カルダンの元でも修行をしている。